お金がなくても、お葬式はできるのでしょうか?
経済的な事情で、「葬儀ができないかもしれない」と不安になる方は少なくありません。
しかし、生活保護を受けている方や、そのご家族には、最低限の葬儀を行うための制度=福祉葬儀(葬祭扶助)が用意されています。
私は葬祭ディレクターとしての現場経験を通して、この制度に助けられた方々を何人も見てきました。今回はその福祉葬儀制度について、現場視点で分かりやすく解説します。
この記事でわかること
福祉葬(葬祭扶助)とは何か、どんな人が利用できるのか
葬祭扶助の申請から葬儀までの流れ
対象となる葬儀費用の範囲と上限額
申請時に注意すべきポイント(葬儀後の申請不可など)
家族ができるサポートと、よくある誤解の整理
3行まとめ
福祉葬は、生活保護を受けている方のために葬儀費用を自治体が負担する制度。
申請には事前の手続きが必須で、葬儀社と福祉事務所の連携が重要です。
まずは「葬儀前に」相談することが、トラブル防止の第一歩になります。
福祉葬儀とは?
福祉葬儀(正式名称:葬祭扶助)とは、生活保護を受けている方や、その扶養義務者が経済的に困窮している場合に利用できる制度で、必要最低限の火葬式を行うための費用が自治体から支給されるものです。
支給対象になるには?
- 申請者が生活保護受給者であることが原則
- 故人の資産がほぼ無いこと
- 扶養義務者が葬儀費用を出せない状態であること
この3点を満たすかどうか、ケースワーカー(福祉課の担当者)が確認します。
葬儀の内容は?
- 原則として 通夜や告別式は無し
- 火葬のみ(いわゆる直葬) の形式
- お坊さんを呼ぶ、花をつける、祭壇を飾るなどは不可
もう迷わない!通夜と告別式の違いを現役葬儀社スタッフがやさしく解説
制度の趣旨が「必要最低限の葬祭」であるため、“いいとこ取り”はできません。何かを加えたい場合は自費で葬儀を行う必要があります。
急ぎで喪服が必要な場合はレンタルが負担が少なく現実的です。
喪服レンタル(Cariru)|黒ネクタイ|黒ストッキング|数珠|袱紗|香典袋セット
利用の流れ
- ご遺族(または関係者)が、役所の福祉課・ケースワーカーに申請
- ケースワーカーが、申請者や故人の経済状況を確認
- 許可が下りた場合、福祉課から葬儀社に連絡が入る
- 葬儀社側からも、ケースワーカーに電話で確認することが通例(名前の聞き取りが必須)
- 火葬日程や搬送などを調整
体調が悪い、看取りが近いと思ったらあらかじめケースワーカーに相談しておくとスムーズです。
よくある質問
Q1. 生活保護“申請中”でも利用できますか?
A. 地域の運用次第です。まずは葬儀前に福祉事務所へ連絡し、担当の指示に従ってください。
Q2. 申請はだれが行いますか?
A. 原則、親族や身元保証人などの関係者が申請人になります。事情がある場合は担当に相談を。
Q3. どんな葬儀形式になりますか?
A. 多くは直葬(火葬式)が前提です。会食・返礼品・供花などは対象外になることが一般的です。
Q4. 宗教者へのお布施は出ますか?
A. 原則対象外です。読経やお布施を希望する場合は自費になる可能性が高いです。
Q5. 火葬場が混んで安置日数が伸びたら?
A. ドライアイス等の必要最低限は対象になり得ますが、運用は地域差あり。必ず事前確認を。
Q6. 香典は受け取っても大丈夫?
A. 取り扱いは地域差があります。金額や用途によっては収入認定の対象になり得るため、担当へ確認を。
Q7. すでに一般葬で契約してしまった…
A. そのままでは対象外になり得ます。すぐに福祉事務所と葬儀社へ連絡し、中止・変更の可否を相談してください。
喪服レンタル(Cariru)|黒ネクタイ|黒ストッキング|数珠|袱紗|香典袋セット
最後に
葬儀の費用や制度の話は、できれば考えたくないテーマかもしれません。
でも、“そのとき”は、いつか必ずやってきます。
もしものときに慌てないために、そして「できる準備はしておきたい」と思うあなたに、この情報が届けば幸いです。
※広告を含みます
死亡・相続の手続きがぜんぶわかる本(最新版) ─ 役所/年金/光熱費などの停止・名義変更を一覧で確認できます。
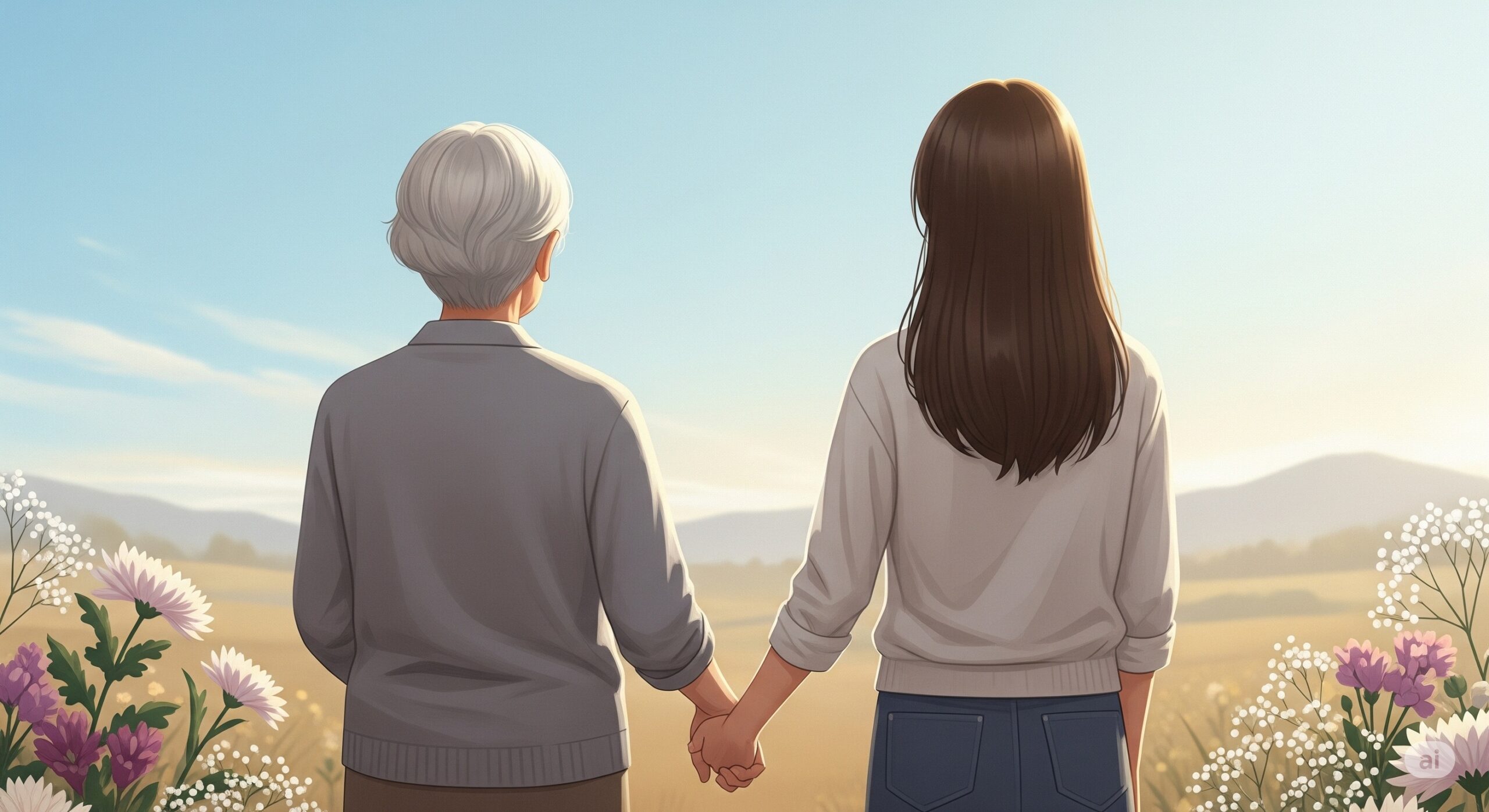


コメント