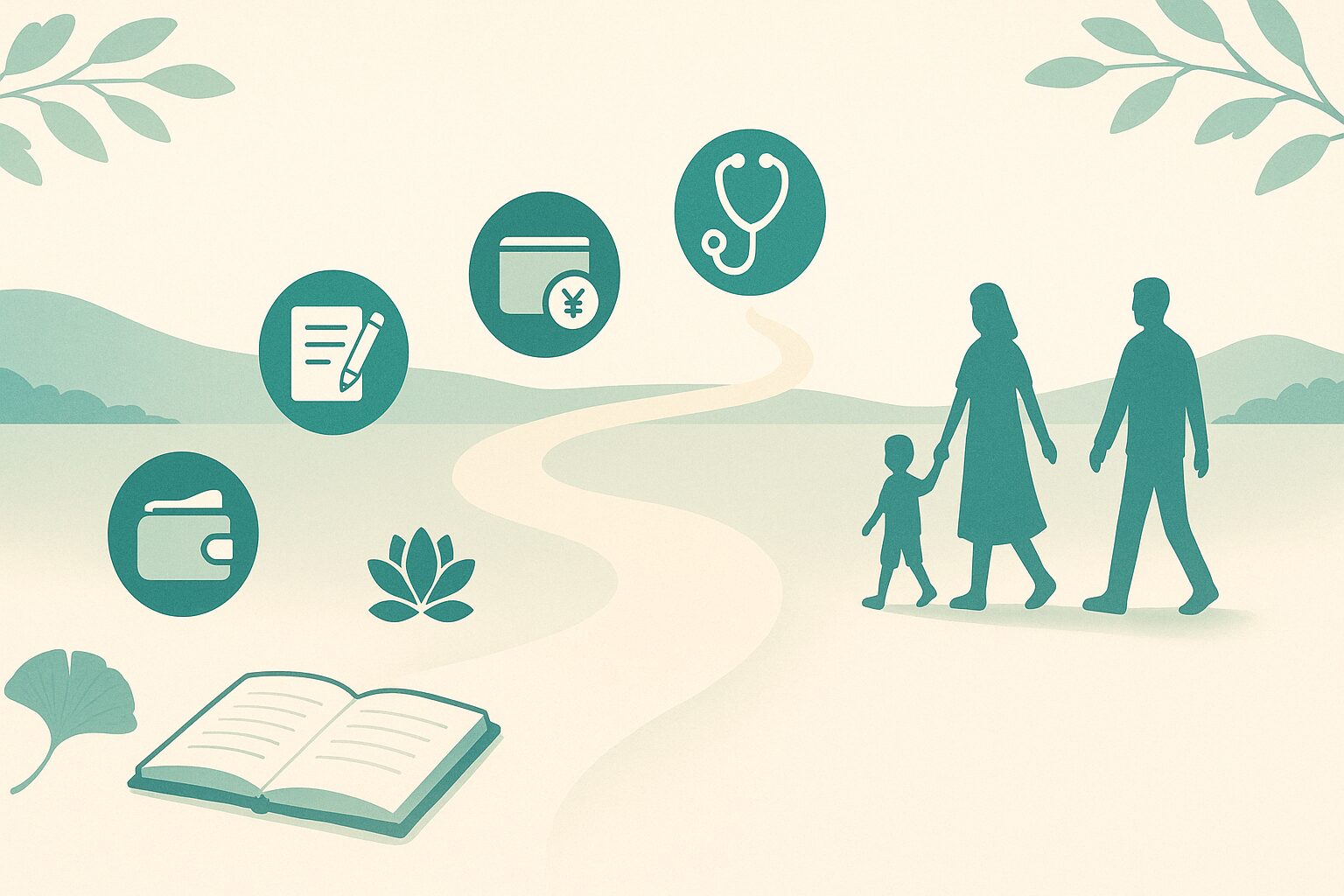「終活、どこから始めればいい?」に静かに答える“全体地図”です。
むずかしい専門用語は最小限に。必要なページへ、最短でたどり着けるようにまとめました。
迷ったら深呼吸して、できるところから一歩ずつ。
※タイプ別の導線は → 終活の入口
終活とは?──全体像がわかる5つの箱
終活は次の5つに分けると、ぐっと楽になります。
- 法的なこと(遺言・相続)
- お金・財産(口座や保険の整理)
- 医療・介護の意思(延命・かかりつけ・連絡先)
- 葬送の希望(葬儀の規模・宗教・お墓)
- 思い出・デジタル(写真・ID・端末のロック)
このページは“要点だけ”を示し、詳しい解説ページへご案内します。
まず決める優先順位(いちばん迷わない順番)
- 意思の可視化(まずは書く)
→ エンディングノートの保管と共有 - 法的な備え(必要な人だけでOK)
→ 遺言書とエンディングノートの違い - 死後の実務を任せる体制
→ 死後事務委任ってなに?実務ガイド - 葬送・お墓の希望を決める
→ お墓を買わないという選択肢(永代供養・樹木葬・納骨堂) - 持ち物・データの整理(継続)
→ 写真・通帳・パスワード類の“置き場所メモ”をノートに(準備中)
全部を完璧にやろうとしないこと。最初の一手は「ノートを1ページだけ埋める」で十分です。
年代・状況別の進め方(ロードマップ)
- 50〜60代:ノート着手/連絡先の代表者を決める → 医療・介護の希望メモ → 葬送の方向性を家族と共有。
- 70代〜:遺言の要否を検討 → 死後事務委任を相談 → 資産一覧を1年に一度見直し。
- おひとり・子どもなし:死後事務委任の優先度が高め。引受先(家族・友人・専門職)を早めに内定。
- 持ち家・お墓あり:承継者の合意形成を先に。維持が難しければ永代供養や納骨堂を検討。
今日できるミニチェックリスト(5分でOK)
- 連絡先の“代表者”を1人決めてノートに書いた
- 健康保険証・通帳・印鑑の置き場所を家族1人と共有した
- 葬儀の希望(規模・宗教・場所)をメモした
- 迷ったら → 終活の入口 で自己診断
よくある質問(FAQ)
Q. エンディングノートがあれば遺言は不要?
A. 法的効力は遺言だけ。財産分けに触れる内容は「遺言」で。ノートは“想いの共有”に。
→ 遺言書とエンディングノートの違い
Q. 葬儀を小さくしても失礼にならない?
A. 事情に合わせて大丈夫。後日のご挨拶や香典返しで丁寧にすれば十分です。
→ 葬儀の基本知識まとめ
Q. お墓は必ず必要?
A. “持たない”選択肢も一般的に。永代供養・樹木葬・納骨堂などを比較して決めましょう。
→ 選択肢の比較ガイド
困ったときの相談先
- 法務・相続:司法書士/弁護士
- 死後事務:行政書士(死後事務委任の契約)
- 葬儀:地元の葬儀社(事前相談・費用の見える化)
- 全体設計:家族会議+エンディングノート
相談は“早いほど安い・楽”。無料相談をうまく使いましょう。
関連ページ(次に読む)
まとめ
終活は“暮らしを整える”やさしい作業です。
完璧より、安心の一歩を。わからないところは、このページから必要なガイドへどうぞ。
→ 終活の入口に戻る / 葬儀の基本知識まとめへ