書いたあと、どうしてる?意外と悩む“保管場所”
エンディングノートを書いてみたはいいけれど、
「これ、どこに置いておけばいいの?」
「家族にどう伝えたらいいんだろう?」
と、ふと悩んでしまったことはありませんか?
実はこの「保管と共有」の部分が、とても大切なんです。
どんなに心を込めて書いても、必要なときに見つけてもらえなければ意味がありません。
この記事では、エンディングノートの保管方法と、家族との共有のコツをやさしくご紹介します。
この記事でわかること
- 見つかる保管の作り方(誰が、どこで、いつ開けるか)
- 紙/デジタルの二重化(3-2-1発想)と更新ルール
- 家族に重くならない共有メッセージの書き方
- 置き場所・封筒ラベル・“開封条件”の最小テンプレ
3行まとめ
- 場所が伝わる=役に立つ。中身より“見つかる保管”が先。
- 紙とデジタルをゆるく二重化して安心を作る。
- 共有は場所と開封条件のみ。季節ごとに軽く更新。
紙?デジタル?それぞれの特徴とおすすめの保管方法
紙のエンディングノート
メリット
- 誰でも読める(スマホやPCが不要)
- 手書きの温かみがある
注意点
- 災害・火事での紛失リスク
- 書き換え・追記がやや面倒
- 「どこにあるか」を誰かに伝えておかないと見つけてもらえない
おすすめ保管場所
- 書類棚や引き出し(家族に「ここにあるよ」と伝える)
- 仏壇や思い出の品のそば
- 金庫(鍵の所在も伝えること)
デジタルのエンディングノート
メリット
- いつでも編集・更新できる
- 複数の人と共有しやすい
- データとしてバックアップができる
注意点
- パスワードが分からないと見られない
- 保存先を知られていないと発見できない
- データ消失リスク(バックアップが必要)
おすすめ保管方法
- クラウドストレージ(Googleドライブ、Dropboxなど)
- Evernote、Notion、Googleドキュメント
- PDFや画像データで保存し、信頼できる人に場所とパスワードのヒントを伝える
家族にどうやって共有すればいい?
一番大事なのは「存在を知らせること」
エンディングノートの良さは、「何かあったときに困らないように、伝えておきたいことをまとめておけること」。
でも、そもそも家族がその存在を知らなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。
少しでも指針があるのと、全くないのでは、遺族の安心感が全く違います。
伝え方のコツ
- 「何かあったときのために書いておいたよ」とサラッと伝える
- 「保険の書類と一緒にしてあるよ」「仏壇の横の棚に入れてあるよ」など、具体的に伝える
- デジタルの場合は、「Googleドライブの“note”フォルダに入れてある」といった説明と、ログイン情報のヒントも忘れずに
- 親しい家族に「このノートの存在を覚えていてね」と頼んでおくのもひとつの方法です
こんな工夫もおすすめ!
- ノートの最初のページに「このノートを見つけてくれてありがとう」と一言添えておく
- カバーや表紙に「エンディングノート在中」と分かるようにしておく
- 複数の場所に「写し」や「ヒントカード」を置いておく(スマホのメモに「重要書類は●●に保管」など)
書くことだけじゃなく、伝えることも終活の一歩
エンディングノートは、ただ「書く」だけでは完結しません。
残すこと、伝えること、見つけてもらうことがそろって、はじめて意味を持ちます。
あなたが大切にしている想いや情報が、
“ちゃんと届く”ようにするために──
今日、ひとつだけでも共有の準備をしてみませんか?
「エンディングノートの場所を家族に伝える」
「スマホのメモに保管場所を書いておく」
小さな一歩が、きっと未来の安心につながります。
関連記事
- エンディングノートって何?20代・30代の“まさか”に備える優しい手紙
- エンディングノートに書いておきたい10のこと(テンプレあり)
- デジタル遺品整理とエンディングノート:SNSやサブスクはどうする?
- 無宗教の人が書くエンディングノート──送り方の希望をどう伝える?
ノートに書くだけじゃなく、身の回りの整理も進めておくとスムーズ
👉生前整理の片付けはどこから?——“10分ルール”で今日から進める小さな手順
※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
- 耐火・防水ケース(書類とUSBの定位置): 耐火・防水ケース
- 外付けSSD(PDF控えと写真バックアップ): 外付けSSD
- A4クリアポケット/仕切りファイル(原本整理): クリアポケット/仕切りファイル
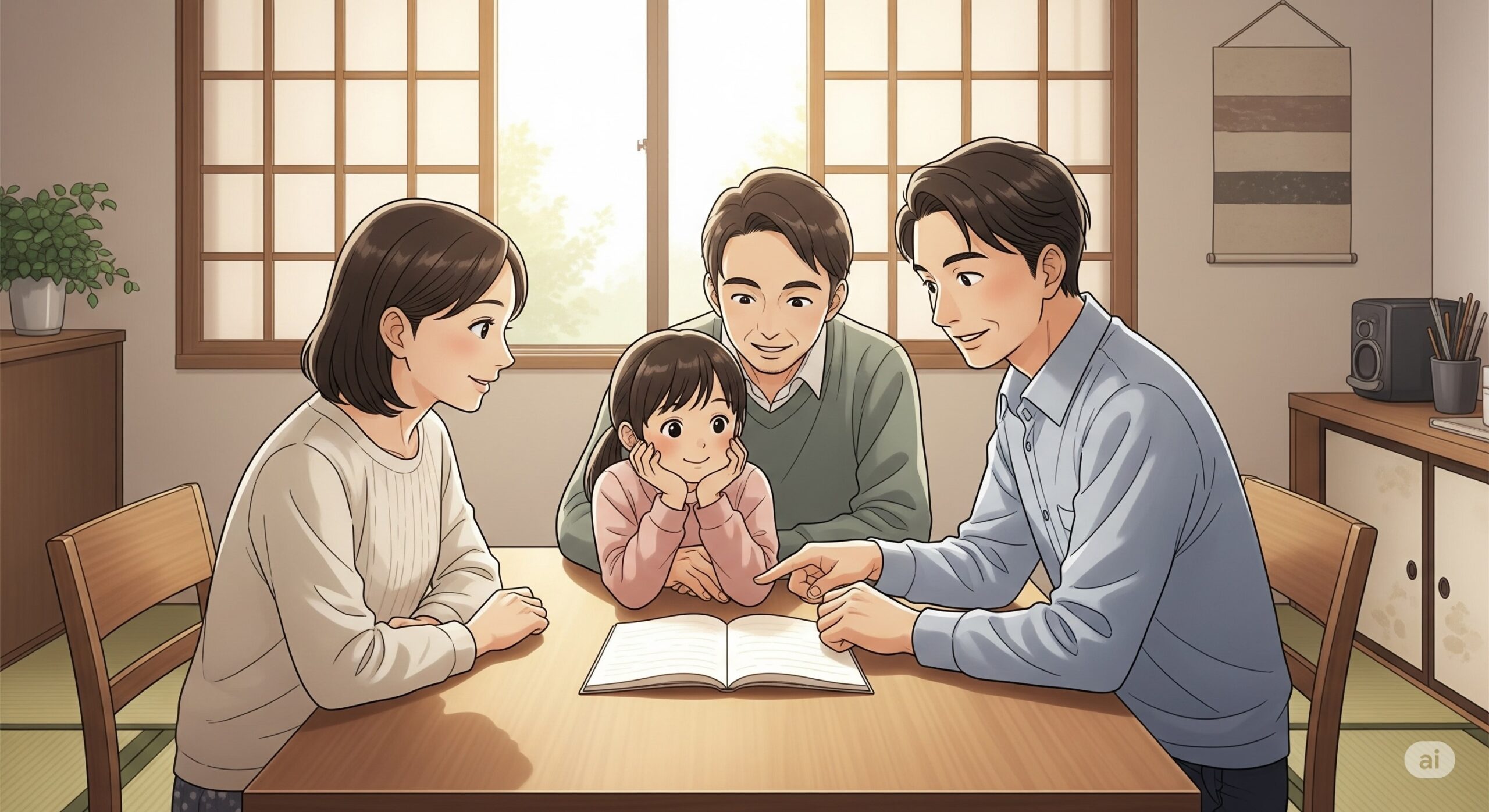


コメント