はじめに
法事の日程が決まると、次に悩みやすいのが「どうやって人を呼ぶか」です。
案内状を出すべきか、LINEや電話で済ませていいのか、往復はがきで出欠を取るべきか…。
いざ文面を書こうとすると、言葉選びや形式で手が止まりやすいところです。
この記事では、葬儀社での現場経験をもとに、
・法事の案内状を「誰に・いつ出すか」の目安
・封書・往復はがきそれぞれの文例
・欠席するときの返信文例(はがき・メール)
・会社や職場への社内メールの書き方
を、「きちんとしつつ無理はしない」ラインでまとめました。
法事全体の流れや準備の優先順位は、次のページで地図のように整理しています。
→ 法事・供養まとめ|時期・立場・目的・方式で探せる入口ページ
「そんなに完璧じゃなくていい」と肩の力を抜きながら、自分たちのペースで整えていきましょう。
この記事でわかること
・法事の案内状を「誰に・いつ・どの形で」送るかの目安
・封書・はがき・往復はがきそれぞれの書き方と文例
・やむを得ず欠席する場合の返信文例(はがき・メール)
・会社や職場への社内メールの書き方と例文
3行まとめ
・法事の案内状は「日程が決まったら1か月前〜2週間前」を目安に、対象を絞って早めに送ると安心です。
・往復はがきや封書の文面は、形式をおさえてしまえばほぼ定型。迷ったら「日時・場所・施主名・返信期限」の4点を必ず入れれば大きくは外れません。
・欠席の返信や社内メールでは「やむを得ない事情」「お詫び」「お悔やみ/感謝」の3点を短く添えれば、丁寧さと読みやすさの両方が保てます。
自宅で完結させたい方は、ネット印刷を使うとラクです。
法事の案内状の基本(誰に・いつ出すか)
「どこまできっちりやるべきか…」と悩んだときは、まずは形よりも「相手が予定を立てやすいか」を軸に考えてあげると、自然と必要な範囲が見えてきます。
法事の案内状は、
・誰に声をかけるか(親族だけか、故人と親しかった友人までか)
・どの規模で行うか(ごく内輪か、葬儀と同じ顔ぶれか)
によって送り先が変わります。
目安としては、
・一周忌:親族+故人と特に親しかった友人・知人
・三回忌以降:親族中心、友人はごく一部
くらいに絞るご家庭が多いです。
タイミングは、
・できれば1か月前〜3週間前
・遅くとも2週間前までに投函
を目安にしておくと、相手も予定を立てやすくなります。
日程や会場を決めるときの全体像は、個別の法要ページも参考になります。
→ 四十九日(満中陰)の流れと準備|数え方・所要時間・服装・香典
→ 一周忌の段取り|案内状はいつ出す?返信期限/会食なしのマナー/返礼相場まで
法事は「親戚だけ・口頭連絡」で済むことも多い
全部を完璧に整えなくても、身内どうしで気持ちが通じていれば十分という場面もたくさんあります。「案内状を出さない=手抜き」ではないので、規模に合わせて気楽に考えてみてください。
ここまで案内状の話をしてきましたが、実際の現場感としては、
親戚だけで行う法要なら「わざわざ案内状を出さない」ご家庭のほうが多いです。
一周忌や三回忌でも、
・両親+きょうだい家族くらいの10人前後
・みんなが近距離に住んでいる
・毎年のように集まっている顔ぶれ
といった場合は、
・電話や口頭で伝える
・家族LINEグループで日時を共有する
だけで済ませることもよくあります。
「ちゃんとした案内状を出さないと失礼」というほどではありません。
むしろ、次のような場合に“紙の案内状”が力を発揮します。
・参加人数が多く、出欠管理が必要なとき
・遠方の親戚や、久しぶりに声をかける方が多いとき
・ホテルや会食会場の予約人数をきっちり固めたいとき
・きょうだい間で「誰にどのように案内したか」を形に残しておきたいとき
ざっくり言えば、
・ごく近い親族だけ → 口頭・LINE中心でもOK
・親族+故人の友人など「少し広めの範囲」 → 案内状があると安心
くらいで考えておけば、大きくは外れません。
どこまで法事を続けるか悩むときは、「何回忌まで」が一つの目安になります。
→ 法要は何回忌まで?三回忌・七回忌・十三回忌の区切りと“弔い上げ”の考え方
- 法要案内向けの文例がある(整った言い回しで迷いにくい)
- 返信はがき(出欠用)を付けられる
- 宛名印刷まで任せると、作業時間が激減する
封書で出す案内状の文例
一度ひな形を作っておけば、名前と日時を差し替えるだけで毎回使いまわせます。「最初の1通」を一緒に整えて、あとは自分の家の定番としてしまいましょう。
一周忌・三回忌あたりで使える、ごくベーシックな文面例です。
「亡父」の部分は「亡母」「祖父」「義父」など、ご状況に合わせて差し替えてください。
(宛名)
○○ ○○ 様
(本文)
拝啓 晩秋の候 皆様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます。
さて 亡父 ○○○○ 一周忌にあたり 下記のとおり法要を執り行いたく存じます。
ご多用のところまことに恐れ入りますが ご都合がゆるしましたらご参列賜りますようご案内申し上げます。
敬具
記
一 日時 令和○年○月○日(○) 午前○時○分より
一 場所 ○○寺
○○市○○町○丁目○番地
電話 ○○−○○○○
なお 誠に勝手ながら 準備の都合上 ○月○日までに同封のはがきにてご出欠をお知らせくださいますようお願い申し上げます。
令和○年○月○日
施主 ○○○○
住所 ○○市○○町○丁目○番地
電話 ○○−○○○○
・時候の挨拶は季節に合わせて差し替えOKです。
・「一周忌」の部分を「三回忌」「七回忌」などに変えても使えます。
案内状とあわせて、「香典やお布施、当日のお返し」も整えたい方は、こちらも参考になると思います。
→ 法事のお布施はいくら包む?金額の考え方と御車代・御膳料・本堂使用料の目安
→ 法事のお返し(引き出物・粗供養)の実務ガイド|相場・商品券・のし・お礼文まで
往復はがきで出欠をとるときの文例
誰が出席してくれるのかを早めに把握できると、会食やお返しの準備もぐっと楽になります。少し手間はかかりますが、「あの人に声がかかっていなかった」という行き違いも防ぎやすくなります。
往復はがきは、
・往信面:案内の本文
・返信面:出欠のチェック欄+一言欄
のセットで考えると楽です。
往信面の文例
拝啓
亡父 ○○○○ 一周忌にあたり 左記のとおり法要を営みたく存じます。
つきましてはご多用中まことに恐縮ですが ご都合のほどお知らせくださいますようお願い申し上げます。
敬具
記
一 日時 令和○年○月○日(○) 午前○時○分より
一 場所 ○○寺(○○市○○町○丁目○番地)
誠に勝手ながら ○月○日までにご返事を頂戴できますと幸いに存じます。
令和○年○月○日
施主 ○○○○
返信面のレイアウト例(文章イメージ)
ご出欠
□ ご出席いたします
□ ご欠席いたします
お名前
ご住所
ご芳情にあらためて御礼申し上げます。
(自由記入欄/一言メッセージ用)
・実際には「ご出席」「ご欠席」の「ご」を二重線で消す、といったマナーもあります。
・細かい作法は地域差も大きいので、「ここまでできれば十分」と思いながら進めても大丈夫です。
はがきに添える一言や、お供え・手土産のことで迷うときは、こちらも覗いてみてください。
→ 法事・法要のお供えは何がいい?花・お菓子・金額・掛け紙の基本ガイド
欠席するときの返信文例(はがき・メール)
どうしても行けないとき、「断ること」よりも「黙ったままになること」のほうが相手は心配になります。短くても一言返しておけば、それだけで十分ていねいな印象になります。
はがきで欠席を伝える文例
前略
このたびはご丁寧なご案内をいただき まことにありがとうございます。
せっかくお声がけいただきながら あいにく所用により当日は出席かないません。
ご無礼をお許しくださいますようお願い申し上げます。
ご法要がつつがなく執り行われますことを 心よりお祈りいたしております。
草々
「所用」の部分は、「仕事の都合」「体調不良」「やむを得ぬ事情により」など、状況に応じて濁して構いません。
メールで欠席を伝える文例(親族・知人向け)
件名:一周忌法要のご案内へのご返信
○○様
このたびはご丁寧なご案内をいただき ありがとうございます。
せっかくお声がけいただきましたが あいにく当日は外せない予定があり 今回は欠席させていただきたく存じます。
ご無礼をお詫び申し上げるとともに ご法要が滞りなく執り行われますようお祈りいたします。
△△△△
欠席しつつ香典だけお送りする場合は、金額や袋の書き方も気になるところだと思います。
→ 香典相場の早見表と正しい書き方(表書き・中袋・連名まで)
会社・職場への社内メール文例
「親族の法事で休みます」と伝えるのは、少し気が引けるかもしれません。でも、事情を簡潔に共有してくれれば、多くの職場ではきちんと理解してもらえます。言いにくさを文章の型でサポートしてもらうイメージで使ってください。
上司あて・事前相談メールの例
件名:○月○日(○)休暇取得のご相談(親族の法事)
○○課長
お疲れさまです。△△です。
私事で恐れ入りますが
○月○日(○)に親族の一周忌法要が予定されており 当日は出席する必要がございます。
つきましては 同日を年次有給休暇として取得させていただきたく存じます。
業務については 事前に○○さんへ引き継ぎのうえ ご迷惑のないよう調整いたします。
ご多用のところ恐れ入りますが ご確認のほどよろしくお願いいたします。
△△△△
同僚あて・社内チャットなどの例
○月○日(○)は 親族の法事でお休みをいただきます。
前日のうちに担当分はできるだけ片づけておきますが 当日分の対応で何かお願いすることがあればまた相談させてください。
ご迷惑をおかけしますが よろしくお願いします。
会社・取引先からの香典や弔電については、会社ごとのルールも関わってきます。
基本の考え方は次のページでまとめています。
→ 香典・弔電の基本まとめ|マナー・文例・受付の実務
弔電だけ急いで送りたいときは、こちらも。
→ 弔電の送り方|本日中・当日・明日届く最短ルート
よくあるつまずきポイントQ&A
細かいところまで「これで合ってるのかな…」と不安になるのは、むしろ真面目に向き合っている証拠です。よくいただく質問を先に押さえておくと、準備の途中で立ち止まる回数がぐっと減ります。
Q1. 葬儀のときと同じ顔ぶれに全部案内を出したほうがいいですか?
A1. 必ずしも同じ範囲でなくて大丈夫です。
一周忌以降は、親族を中心に「普段も付き合いのある方」へ声をかけるご家庭が多くなります。
故人のご友人など、葬儀のときに来てくださった方へお声がけするかどうかは、
・今も交流があるか
・遠方から来ていただく負担が大きすぎないか
などを見ながら、家族で話し合って決めてかまいません。
Q2. 返信期限までに返事が来ない人がいて困ります…
A2. まずは電話やメールで一度だけ、やわらかく確認してみましょう。
「会食の人数をお店に伝える都合があって…」と理由を添えると、相手も返事をしやすくなります。
最終的にどうしても連絡が取れない場合は、「欠席扱い」にしておき、当日もし来られたらできる範囲で対応する、くらいの気持ちでよいと思います。
Q3. 会食は親族だけですが、法要自体は友人にも開きたい場合、案内文は分けたほうがいいですか?
A3. 分けられるなら分けたほうが、相手が迷いにくくなります。
例えば、親族向けには「法要+会食のご案内」、友人向けには「法要のみのご案内」として、会食の案内部分だけ文面から外すイメージです。
そこまで分ける余裕がない場合は、案内状に小さく「会食は親族のみで失礼いたします」と添えるだけでも伝わりやすくなります。
まとめ
法事の案内状に「正解の一枚」はありません。相手への気づかいと、今の自分たちが無理なく続けられる形、そのちょうどよいところを探していければ、それで十分ていねいなご案内になります。
文章の型さえ一度つくっておけば、次回以降は日付と名前を入れ替えるだけで使いまわせます。
今回の記事をベースに、自分の家なりの「定番文面」をひとつ持っておいてもらえたらうれしいです。
あわせて読んでおくと、法事まわりの準備がひと通りそろいます。
・お供えの基本と選び方
→ 法事・法要のお供えは何がいい?花・お菓子・金額・掛け紙の基本ガイド
・お返し・粗供養の実務ガイド
→ 法事のお返し(引き出物・粗供養)の実務ガイド|相場・商品券・のし・お礼文まで
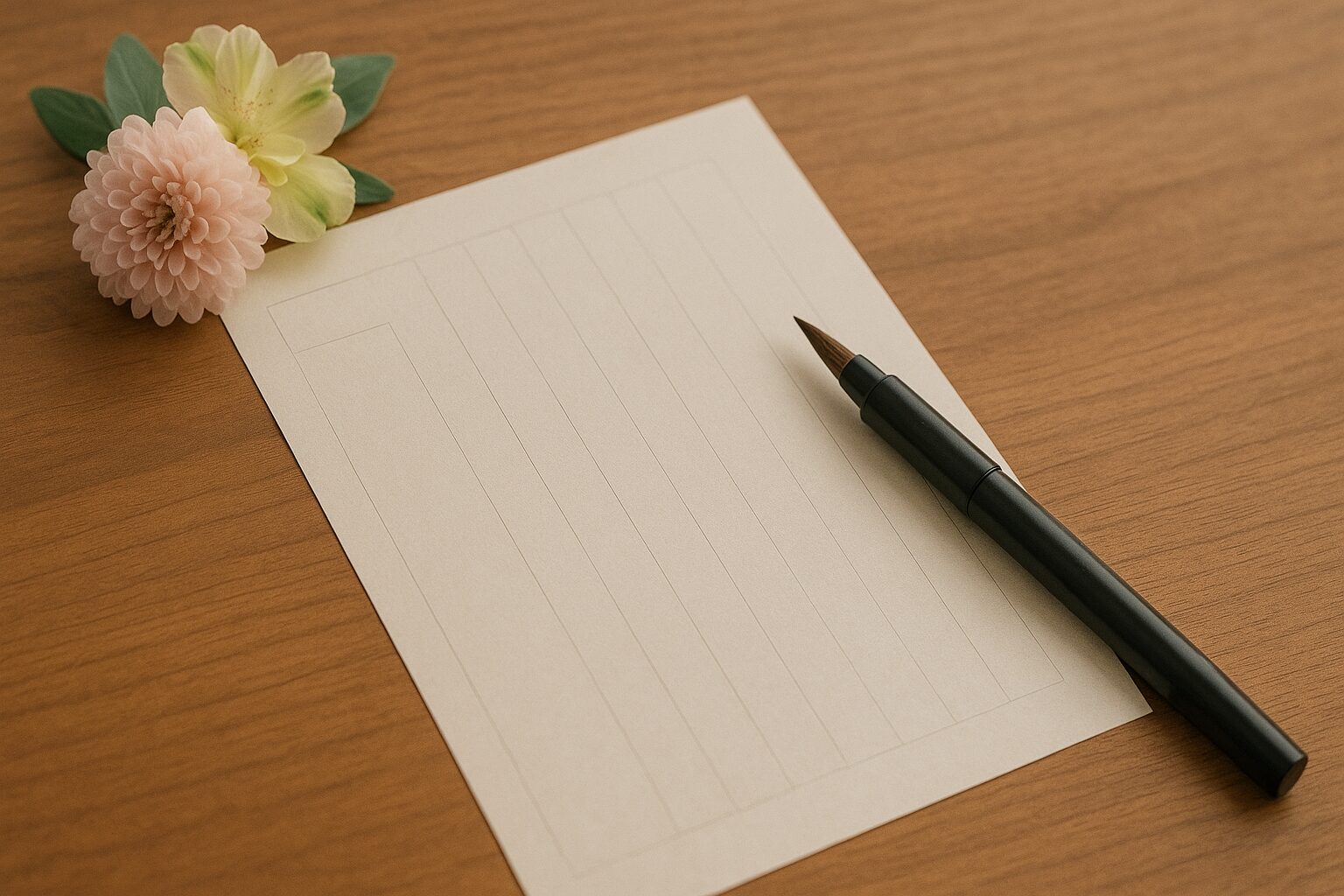


コメント